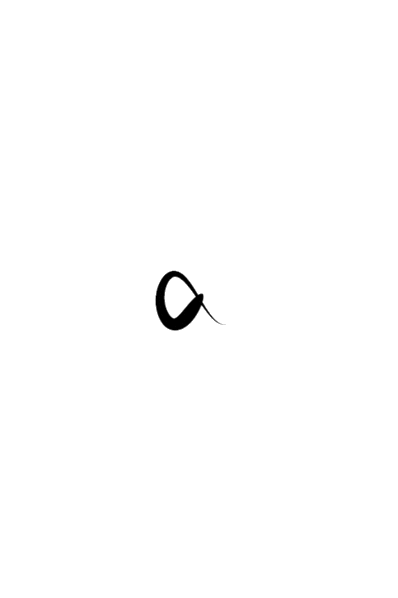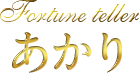安心・平穏・喜び・夢・希望・幸せ 占あかり いつもあなたの全てが 人生の 価値ある ひと時に、、、 | ★★ 占い鑑定 相談料金 ★★ 一般 1500円 30分 (30分から10分ごと500円追加) ご予約・お問合せ (10~22時受付) ✉ メール (24時間受付) |
お知らせ
占い師たかしのメルマガ配信中!
ココでしか聞けない裏話、日常に役立つあれこれ、メルマガを通じ無料で配信しています。占いの知識、時事、仕事、金運アップ術、男と女、家族、自信と誇りの回復、人生の幸せあれこれ、楽しく、また様々な情報盛りだくさん配信中です。
▼ ご登録はこちら ▼
【馬渕睦夫】世界中で日本人だけが持つ〇〇という能力。日本人の皆さん、たった12分ですので、馬渕先生のお話を聞いて日本人の底力に気付いてください。
馬渕睦夫 ( まぶち むつお ) のYouTubeチャンネル
【未来ネットチャンネル】 馬渕睦夫 ( まぶち むつお ) の公式YouTubeチャンネル

◆◆◆◆◆◆◆◆略 歴◆◆◆◆◆◆◆◆ 京都府船井郡八木町日置出身。八木町立富本小学校、 福知山市立大江中学校、京都府立園部高等学校第16回を経て、 京都大学法学部3年次在学中に外務公務員採用上級試験に 合格し中退、1968年(昭和43年)に外務省入省。 研修先であったイギリスのケンブリッジ大学経済学部に入学し、 1971年(昭和46年)に卒業 外務本省では、国際連合局社会協力課長(1984年-1986年)、 大臣官房文化交流部文化第一課長、東京都外務長(1995年-1997年) などを歴任 在外では、在英国日本国大使館、在インド日本国大使館、 在ソビエト連邦日本国大使館、在ニューヨーク日本国 総領事館に勤務し、EC代表部参事官(1989年-1991年) 在イスラエル日本大使館公使(1991年-1995年) 在タイ日本大使館特命全権公使(1997年-2000年)を務めた 2000年(平成13年)に特命全権大使キューバ国駐箚に就任 2003年(平成15年)5月には財団法人国際開発高等教育機構 専務理事に就任し、2005年(平成17年)より駐ウクライナ 兼モルドバ大使を3年間務め、2008年(平成20年)11月、 外務省退官。同月防衛大学校教授に就任し、2011年 (平成23年)3月、定年退職。 #馬渕睦夫 #ひとりがたり #馬渕大使
<馬淵先生のお話を拝聴させて頂き、あかりの感じた考察>
作り変え同化していく、または同化させていく力が秀でている日本は、
この特殊能力をまだ、外来の文化に対して十分に発揮が出来ていません。
特に、外来の啓蒙思想はじめ空想の産物に、自分がわからないまま、
心のもやもやを無視し、無理やり合わせていますと、
大切に守るべき事に気づかないまま、
さらに自分を失い破壊、自滅に陥ってしまいます。
またそれは、日本を失ってしまうことにも繋がって行きます。
日本人だけが持つ万年を保ってきた日本化する能力、
または、日本化へ土着化させる能力へ、
作り変え同化させる特殊な能力を発揮しなければなりません。
そうすれば、戦後から続く精神の混乱が終わります。
当たり前の中身が空っぽになってしまっているのに、
わかっているつもりだけでは危険です。破壊が進む一方です。
特に、日本は、戦後から様々にわたり大胆に国体を破壊されました。
その中で、日本人の精神の命である大和心やその精神を破壊する為に、
健全な国体の状態であれば、伝えられるべき知恵、感性を
公的機関や身近な生活から完全に彼らは消してきました。
多くの方が空想世界の折の中に閉じ込められている状態です。
日本の深い情感や感性は物体化してしまい、
自らがわからない状態になり、自らの判断が出来ず、
流行り、ルールや権力、権威に従順に従う人間ばかりになってしまっています。
それだけに、多数の場面で、日本人らしからぬ問題言動行動が多発しています。
日々の生活に、夢、希望、精神の余裕が無くなり、日々の生活が居心地が悪くなっています。
日本人が、一人ひとりが持っている特殊な能力を発揮する時です。
自らの特殊能力を復活させ、戦後の不必要は排除し、
必要なものを加え、修正し、他を日本文化に同化させ豊かにする
日本化を実施する時が来ました。行動に移しましょう。
————————————————————————————————-
動画内で紹介された本について
奉教人の死(芥川龍之介) 神神の微笑(芥川龍之介)は以下に全文書き下し
國體の本義は、以下のURL紹介ページへどうぞ。
國 體 の 本 義 1937年(昭和12)3月30日 文部省 発行
國體の本義全文はこちらをどうぞ↓↓
https://binder.gozaru.jp/kokutainohongi.htm
国立国会図書館の近代デジタルライブラリーの國體の本義(1937年刊)
奉教人の死
芥川龍之介
+目次
たとひ三百歳の齢よはひを保ち、楽しみ身に余ると云ふとも、未来永々の果しなき楽しみに比ぶれば、夢幻ゆめまぼろしの如し。
―慶長訳 Guia do Pecador―
善の道に立ち入りたらん人は、御教みをしへにこもる不可思議の甘味を覚ゆべし。
―慶長訳 Imitatione Christi―
一
去さんぬる頃、日本長崎の「さんた・るちや」と申す「えけれしや」(寺院)に、「ろおれんぞ」と申すこの国の少年がござつた。これは或年御降誕の祭の夜、その「えけれしや」の戸口に、餓ゑ疲れてうち伏して居つたを、参詣の奉教人衆ほうけうにんしゆうが介抱し、それより伴天連ばてれんの憐みにて、寺中に養はれる事となつたげでござるが、何故かその身の素性すじやうを問へば、故郷ふるさとは「はらいそ」(天国)父の名は「でうす」(天主)などと、何時も事もなげな笑に紛らいて、とんとまことは明した事もござない。なれど親の代から「ぜんちよ」(異教徒)の輩ともがらであらなんだ事だけは、手くびにかけた青玉あをだまの「こんたつ」(念珠)を見ても、知れたと申す。されば伴天連はじめ、多くの「いるまん」衆(法兄弟)も、よも怪しいものではござるまいとおぼされて、ねんごろに扶持して置かれたが、その信心の堅固なは、幼いにも似ず「すぺりおれす」(長老衆)が舌を捲くばかりであつたれば、一同も「ろおれんぞ」は天童の生れがはりであらうずなど申し、いづくの生れ、たれの子とも知れぬものを、無下むげにめでいつくしんで居つたげでござる。
して又この「ろおれんぞ」は、顔かたちが玉のやうに清らかであつたに、声ざまも女のやうに優しかつたれば、一ひとしほ人々のあはれみを惹ひいたのでござらう。中でもこの国の「いるまん」に「しめおん」と申したは、「ろおれんぞ」を弟おととのやうにもてなし、「えけれしや」の出入りにも、必かならず仲よう手を組み合せて居つた。この「しめおん」は、元さる大名に仕へた、槍一すぢの家がらなものぢや。されば身のたけも抜群なに、性得しやうとくの剛力であつたに由つて、伴天連が「ぜんちよ」ばらの石瓦にうたるるを、防いで進ぜた事も、一度二度の沙汰ではごさない。それが「ろおれんぞ」と睦むつまじうするさまは、とんと鳩になづむ荒鷲のやうであつたとも申さうか。或は「ればのん」山の檜ひのきに、葡萄えびかづらが纏まとひついて、花咲いたやうであつたとも申さうず。
さる程に三年あまりの年月は、流るるやうにすぎたに由つて、「ろおれんぞ」はやがて元服もすべき時節となつた。したがその頃怪しげな噂が伝はつたと申すは、「さんた・るちや」から遠からぬ町方の傘張の娘が、「ろおれんぞ」と親しうすると云ふ事ぢや。この傘張の翁おきなも天主の御教を奉ずる人故、娘ともども「えけれしや」へは参る慣ならはしであつたに、御祈の暇にも、娘は香炉をさげた「ろおれんぞ」の姿から、眼を離したと申す事がござない。まして「えけれしや」への出入りには、必かならず髪かたちを美しうして、「ろおれんぞ」のゐる方へ眼づかひをするが定ぢやうであつた。さればおのづと奉教人衆の人目にも止り、娘が行きずりに「ろおれんぞ」の足を踏んだと云ひ出すものもあれば、二人が艶書をとりかはすをしかと見とどけたと申すものも、出て来たげでござる。
由つて伴天連にも、すて置かれず思おぼされたのでござらう。或日「ろおれんぞ」を召されて、白ひげを噛みながら、「その方、傘張の娘と兎角の噂ある由を聞いたが、よもやまことではあるまい。どうぢや」ともの優しう尋ねられた。したが「ろおれんぞ」は、唯ただ憂はしげに頭を振つて、「そのやうな事は一向に存じよう筈もござらぬ」と、涙声に繰返すばかり故、伴天達もさすがに我がを折られて、年配と云ひ、日頃の信心と云ひ、かうまで申すものに偽はあるまいと思されたげでござる。
さて一応伴天連の疑うたがひは晴れてぢやが、「さんた・るちや」へ参る人々の間では、容易にとかうの沙汰が絶えさうもござない。されば兄弟同様にして居つた「しめおん」の気がかりは、又人一倍ぢや。始はかやうな淫みだらな事を、ものものしう詮議立てするが、おのれにも恥しうて、うちつけに尋ねようは元より、「ろおれんぞ」の顔さへまさかとは見られぬ程であつたが、或時「さんた・るちや」の後の庭で、「ろおれんぞ」へ宛てた娘の艶書を拾うたに由つて、人気ひとけない部屋にゐたを幸さいはひ、「ろおれんぞ」の前にその文をつきつけて、嚇おどしつ賺すかしつ、さまざまに問ひただいた。なれど「ろおれんぞ」は唯、美しい顔を赤らめて、「娘は私に心を寄せましたげでござれど、私は文を貰うたばかり、とんと口を利きいた事もござらぬ」と申す。なれど世間のそしりもある事でござれば、「しめおん」は猶なほも押して問ひ詰なじつたに、「ろおれんぞ」はわびしげな眼で、ぢつと相手を見つめたと思へば、「私はお主ぬしにさへ、嘘をつきさうな人間に見えるさうな」と、咎とがめるやうに云ひ放つて、とんと燕つばくろか何ぞのやうに、その儘つと部屋を立つて行つてしまうた。かう云はれて見れば、「しめおん」も己の疑深かつたのが恥しうもなつたに由つて、悄々すごすごその場を去らうとしたに、いきなり駈けこんで来たは、少年の「ろおれんぞ」ぢや。それが飛びつくやうに「しめおん」の頸うなじを抱くと、喘あへぐやうに「私が悪かつた。許して下されい」と囁ささやいて、こなたが一言ひとことも答へぬ間に、涙に濡れた顔を隠さう為か、相手をつきのけるやうに身を開いて、一散に又元来た方へ、走つて往いんでしまうたと申す。さればその「私が悪かつた」と囁いたのも、娘と密通したのが悪かつたと云ふのやら、或は「しめおん」につれなうしたのが悪かつたと云ふのやら、一円合点いちゑんがてんの致さうやうがなかつたとの事でござる。
するとその後間もなう起つたのは、その傘張の娘が孕みごもつたと云ふ騒ぎぢや。しかも腹の子の父親は、「さんた・るちや」の「ろおれんぞ」ぢやと、正まさしう父の前で申したげでござる。されば傘張の翁は火のやうに憤いきどほつて、即刻伴天連のもとへ委細を訴へに参つた。かうなる上は「ろおれんぞ」も、かつふつ云ひ訳の致しやうがござない。その日の中に伴天連を始め、「いるまん」衆一同の談合に由つて、破門を申し渡される事になつた。元より破門の沙汰がある上は、伴天連の手もとをも追ひ払はれる事でござれば、糊口のよすがに困るのも目前ぢや。したがかやうな罪人を、この儘「さんた・るちや」に止めて置いては、御主おんあるじの「ぐろおりや」(栄光)にも関かかはる事ゆゑ、日頃親しう致いた人々も、涙をのんで「ろおれんぞ」を追ひ払つたと申す事でござる。
その中でも哀れをとどめたは、兄弟のやうにして居つた「しめおん」の身の上ぢや。これは「ろおれんぞ」が追ひ出されると云ふ悲しさよりも、「ろおれんぞ」に欺かれたと云ふ腹立たしさが一倍故、あのいたいけな少年が、折からの凩こがらしが吹く中へ、しをしをと戸口を出かかつたに、傍から拳こぶしをふるうて、したたかその美しい顔を打つた。「ろおれんぞ」は剛力に打たれたに由つて、思はずそこへ倒れたが、やがて起きあがると、涙ぐんだ眼で、空を仰ぎながら、「御主も許させ給へ。『しめおん』は、己おのが仕業もわきまへぬものでござる」と、わななく声で祈つたと申す事ぢや。「しめおん」もこれには気が挫けたのでござらう。暫くは唯戸口に立つて、拳を空くうにふるうて居つたが、その外の「いるまん」衆も、いろいろととりないたれば、それを機会しほに手を束つかねて、嵐も吹き出でようず空の如く、凄すさまじく顔を曇らせながら、悄々すごすご「さんた・るちや」の門を出る「ろおれんぞ」の後姿を、貪るやうにきつと見送つて居つた。その時居合はせた奉教人衆の話を伝へ聞けば、時しも凩にゆらぐ日輪が、うなだれて歩む「ろおれんぞ」の頭のかなた、長崎の西の空に沈まうず景色であつたに由つて、あの少年のやさしい姿は、とんと一天の火焔の中に、立ちきはまつたやうに見えたと申す。
その後の「ろおれんぞ」は、「さんた・るちや」の内陣に香炉をかざした昔とは打つて変つて、町はづれの非人小屋に起き伏しする、世にも哀れな乞食こつじきであつた。ましてその前身は、「ぜんちよ」の輩ともがらにはゑとりのやうにさげしまるる、天主の御教を奉ずるものぢや。されば町を行けば、心ない童部わらべに嘲あざけらるるは元より、刀杖瓦石たうぢやうぐわせきの難に遭あうた事も、度々ござるげに聞き及んだ。いや、嘗かつては、長崎の町にはびこつた、恐しい熱病にとりつかれて、七日七夜の間、道ばたに伏しまろんでは、苦み悶もだえたとも申す事でござる。したが、「でうす」無量無辺の御愛憐は、その都度「ろおれんぞ」が一命を救はせ給うたのみか、施物の米銭のない折々には、山の木の実、海の魚介など、その日の糧かてを恵ませ給ふのが常であつた。由つて「ろおれんぞ」も、朝夕の祈は「さんた・るちや」に在つた昔を忘れず、手くびにかけた「こんたつ」も、青玉の色を変へなかつたと申す事ぢや。なんの、それのみか、夜毎に更闌かうたけて人音も静まる頃となれば、この少年はひそかに町はづれの非人小屋を脱け出いだいて、月を踏んでは住み馴れた「さんた・るちや」へ、御主「ぜす・きりしと」の御加護を祈りまゐらせに詣でて居つた。
なれど同じ「えけれしや」に詣づる奉教人衆も、その頃はとんと「ろおれんぞ」を疎うとんじはてて、伴天連はじめ、誰一人憐みをかくるものもござらなんだ。ことわりかな、破門の折から所行無慚しよぎやうむざんの少年と思ひこんで居つたに由つて、何として夜毎に、独り「えけれしや」へ参る程の、信心ものぢやとは知られうぞ。これも「でうす」千万無量の御計らひの一つ故、よしない儀とは申しながら、「ろおれんぞ」が身にとつては、いみじくも亦哀れな事でござつた。
さる程に、こなたはあの傘張の娘ぢや。「ろおれんぞ」が破門されると間もなく、月も満たず女の子を産み落いたが、さすがにかたくなしい父の翁も、初孫の顔は憎からず思うたのでござらう、娘ともども大切に介抱して、自ら抱きもしかかへもし、時にはもてあそびの人形などもとらせたと申す事でござる。翁は元よりさもあらうずなれど、ここに稀有けうなは「いるまん」の「しめおん」ぢや。あの「ぢやぼ」(悪魔)をも挫ひしがうず大男が、娘に子が産まれるや否や、暇ある毎に傘張の翁を訪れて、無骨な腕に幼子を抱き上げては、にがにがしげな顔に涙を浮べて、弟と愛いつくしんだ、あえかな「ろおれんぞ」の優姿を、思ひ慕つて居つたと申す。唯、娘のみは、「さんた・るちや」を出でてこの方、絶えて「ろおれんぞ」が姿を見せぬのを、怨めしう歎きわびた気色けしきであつたれば、「しめおん」の訪れるのさへ、何かと快からず思ふげに見えた。
この国の諺ことわざにも、光陰に関守せきもりなしと申す通り、とかうする程に、一年ひととせあまりの年月は、瞬またたくひまに過ぎたと思召おぼしめされい。ここに思ひもよらぬ大変が起つたと申すは、一夜の中に長崎の町の半ばを焼き払つた、あの大火事のあつた事ぢや。まことにその折の景色の凄じさは、末期まつごの御裁判おんさばきの喇叭らつぱの音が、一天の火の光をつんざいて、鳴り渡つたかと思はれるばかり、世にも身の毛のよだつものでござつた。その時、あの傘張の翁の家は、運悪う風下にあつたに由つて、見る見る焔に包れたが、さて親子眷族けんぞく、慌てふためいて、逃げ出いだいて見れば、娘が産んだ女の子の姿が見えぬと云ふ始末ぢや。一定いちぢやう、一間ひとまどころに寝かいて置いたを、忘れてここまで逃げのびたのであらうず。されば翁は足ずりをして罵りわめく。娘も亦、人に遮さへぎられずば、火の中へも馳はせ入つて、助け出さう気色けしきに見えた。なれど風は益ますます加はつて、焔の舌は天上の星をも焦さうず吼たけりやうぢや。それ故火を救ひに集つた町方の人々も、唯、あれよあれよと立ち騒いで、狂気のやうな娘をとり鎮めるより外に、せん方も亦あるまじい。所へひとり、多くの人を押しわけて、馳かけつけて参つたは、あの「いるまん」の「しめおん」でござる。これは矢玉の下もくぐつたげな、逞しい大丈夫でござれば、ありやうを見るより早く、勇んで焔の中へ向うたが、あまりの火勢に辟易へきえき致いたのでござらう。二三度煙をくぐつたと見る間に、背そびらをめぐらして、一散に逃げ出いた。して翁と娘とが佇たたずんだ前へ来て、「これも『でうす』万事にかなはせたまふ御計らひの一つぢや。詮ない事とあきらめられい」と申す。その時翁の傍から、誰とも知らず、高らかに「御主おんあるじ、助け給へ」と叫ぶものがござつた。声ざまに聞き覚えもござれば、「しめおん」が頭かうべをめぐらして、その声の主をきつと見れば、いかな事、これは紛まがひもない「ろおれんぞ」ぢや。清らかに痩せ細つた顔は、火の光に赤うかがやいて、風に乱れる黒髪も、肩に余るげに思はれたが、哀れにも美しい眉目みめのかたちは、一目見てそれと知られた。その「ろおれんぞ」が、乞食の姿のまま、群むらがる人々の前に立つて、目もはなたず燃えさかる家を眺めて居る。と思うたのは、まことに瞬またたく間もない程ぢや。一しきり焔を煽あふつて、恐しい風が吹き渡つたと見れば、「ろおれんぞ」の姿はまつしぐらに、早くも火の柱、火の壁、火の梁うつばりの中にはいつて居つた。「しめおん」は思はず遍身に汗を流いて、空高く「くるす」(十字)を描きながら、己も「御主、助け給へ」と叫んだが、何故かその時心の眼には、凩こがらしに揺るる日輪の光を浴びて、「さんた・るちや」の門に立ちきはまつた、美しく悲しげな、「ろおれんぞ」の姿が浮んだと申す。
なれどあたりに居つた奉教人衆は、「ろおれんぞ」が健気けなげな振舞に驚きながらも、破戒の昔を忘れかねたのでもござらう。忽たちまち兎角の批判は風に乗つて、人どよめきの上を渡つて参つた。と申すは、「さすが親子の情あひは争はれぬものと見えた。己が身の罪を恥ぢて、このあたりへは影も見せなんだ『ろおれんぞ』が、今こそ一人子の命を救はうとて、火の中へはいつたぞよ」と、誰ともなく罵りかはしたのでござる。これには翁おきなさへ同心と覚えて、「ろおれんぞ」の姿を眺めてからは、怪しい心の騒ぎを隠さうず為か、立ちつ居つ身を悶えて、何やら愚おろかしい事のみを、声高こわだかわめいて[#「わめいて」は底本では「わめいつて」]居つた。なれど当の娘ばかりは、狂ほしく大地に跪ひざまづいて、両の手で顔をうづめながら、一心不乱に祈誓を凝こらいて、身動きをする気色さへもござない。その空には火の粉が雨のやうに降りかかる。煙も地を掃はらつて、面おもてを打つた。したが娘は黙然と頭を垂れて、身も世も忘れた祈り三昧ざんまいでござる。
とかうする程に、再ふたたび火の前に群つた人々が、一度にどつとどよめくかと見れば、髪をふり乱いた「ろおれんぞ」が、もろ手に幼子をかい抱いて、乱れとぶ焔の中から、天あまくだるやうに姿を現あらはいた。なれどその時、燃え尽きた梁うつばりの一つが、俄にはかに半ばから折れたのでござらう。凄じい音と共に、一なだれの煙焔えんえんが半空なかぞらに迸ほとばしつたと思ふ間もなく、「ろおれんぞ」の姿ははたと見えずなつて、跡には唯火の柱が、珊瑚の如くそば立つたばかりでござる。
あまりの凶事に心も消えて、「しめおん」をはじめ翁まで、居あはせた程の奉教人衆は、皆目の眩くらむ思ひがござつた。中にも娘はけたたましう泣き叫んで、一度は脛はぎもあらはに躍り立つたが、やがて雷いかづちに打たれた人のやうに、そのまま大地にひれふしたと申す。さもあらばあれ、ひれふした娘の手には、何時かあの幼い女の子が、生死不定しやうじふぢやうの姿ながら、ひしと抱かれて居つたをいかにしようぞ。ああ、広大無辺なる「でうす」の御知慧おんちゑ、御力は、何とたたへ奉る詞ことばだにござない。燃え崩れる梁に打たれながら、「ろおれんぞ」が必死の力をしぼつて、こなたへ投げた幼子は、折よく娘の足もとへ、怪我もなくまろび落ちたのでござる。
されば娘が大地にひれ伏して、嬉し涙に咽むせんだ声と共に、もろ手をさしあげて立つた翁の口からは、「でうす」の御慈悲をほめ奉る声が、自らおごそかに溢れて参つた。いや、まさに溢れようずけはひであつたとも申さうか。それより先に「しめおん」は、さかまく火の嵐の中へ、「ろおれんぞ」を救はうず一念から、真一文字に躍りこんだに由つて、翁の声は再ふたたび気づかはしげな、いたましい祈りの言ことばとなつて、夜空に高くあがつたのでござる。これは元より翁のみではござない。親子を囲んだ奉教人衆は、皆一同に声を揃へて、「御主、助け給へ」と、泣く泣く祈りを捧げたのぢや。して「びるぜん・まりや」の御子みこ、なべての人の苦しみと悲しみとを己おのがものの如くに見そなはす、われらが御主「ぜす・きりしと」は、遂にこの祈りを聞き入れ給うた。見られい。むごたらしう焼けただれた「ろおれんぞ」は、「しめおん」が腕に抱かれて、早くも火と煙とのただ中から、救ひ出されて参つたではないか。
なれどその夜の大変は、これのみではござなんだ。息も絶え絶えな「ろおれんぞ」が、とりあへず奉教人衆の手に舁かかれて、風上にあつたあの「えけれしや」の門へ横へられた時の事ぢや。それまで幼子を胸に抱きしめて、涙にくれてゐた傘張の娘は、折から門へ出でられた伴天連の足もとに跪ひざまづくと、並み居る人々の目前で、「この女子をなごは『ろおれんぞ』様の種ではおぢやらぬ。まことは妾が家隣の『ぜんちよ』の子と密通して、まうけた娘でおぢやるわいの」と思ひもよらぬ「こひさん」(懴悔)を仕つかまつた。その思ひつめた声ざまの震へと申し、その泣きぬれた双の眼のかがやきと申し、この「こひさん」には、露ばかりの偽さへ、あらうとは思はれ申さぬ。道理ことわりかな、肩を並べた奉教人衆は、天を焦がす猛火も忘れて、息さへつかぬやうに声を呑んだ。
娘が涙ををさめて、申し次いだは、「妾は日頃『ろおれんぞ』様を恋ひ慕うて居つたなれど、御信心の堅固さからあまりにつれなくもてなされる故、つい怨む心も出て、腹の子を『ろおれんぞ』様の種と申し偽り、妾につらかつた口惜しさを思ひ知らさうと致いたのでおぢやる。なれど『ろおれんぞ』様のお心の気高さは、妾が大罪をも憎ませ給はいで、今宵は御身の危さをもうち忘れ、『いんへるの』(地獄)にもまがふ火焔の中から、妾娘の一命を辱かたじけなくも救はせ給うた。その御憐み、御計らひ、まことに御主『ぜす・きりしと』の再来かともをがまれ申す。さるにても妾が重々の極悪を思へば、この五体は忽たちまち『ぢやぼ』の爪にかかつて、寸々に裂かれようとも、中々怨む所はおぢやるまい。」娘は「こひさん」を致いも果てず、大地に身を投げて泣き伏した。
二重三重ふたへみへに群つた奉教人衆の間から、「まるちり」(殉教)ぢや、「まるちり」ぢやと云ふ声が、波のやうに起つたのは、丁度この時の事でござる。殊勝にも「ろおれんぞ」は、罪人を憐む心から、御主「ぜす・きりしと」の御行跡を踏んで、乞食にまで身を落いた。して父と仰ぐ伴天連も、兄とたのむ「しめおん」も、皆その心を知らなんだ。これが「まるちり」でなうて、何でござらう。
したが、当の「ろおれんぞ」は、娘の「こひさん」を聞きながらも、僅に二三度頷うなづいて見せたばかり、髪は焼け肌は焦げて、手も足も動かぬ上に、口をきかう気色けしきさへも今は全く尽きたげでござる。娘の「こひさん」に胸を破つた翁と「しめおん」とは、その枕がみに蹲うづくまつて、何かと介抱を致いて居つたが、「ろおれんぞ」の息は、刻々に短うなつて、最期さいごももはや遠くはあるまじい。唯、日頃と変らぬのは、遙に天上を仰いで居る、星のやうな瞳の色ばかりぢや。
やがて娘の「こひさん」に耳をすまされた伴天連は、吹き荒すさぶ夜風に白ひげをなびかせながら、「さんた・るちや」の門を後にして、おごそかに申されたは、「悔い改むるものは、幸さいはひぢや。何しにその幸なものを、人間の手に罰しようぞ。これより益ますます、『でうす』の御戒おんいましめを身にしめて、心静に末期まつごの御裁判おんさばきの日を待つたがよい。又『ろおれんぞ』がわが身の行儀を、御主『ぜす・きりしと』とひとしく奉らうず志は、この国の奉教人衆の中にあつても、類たぐひ稀なる徳行でござる。別して少年の身とは云ひ――」ああ、これは又何とした事でござらうぞ。ここまで申された伴天連は、俄にはかにはたと口を噤つぐんで、あたかも「はらいそ」の光を望んだやうに、ぢつと足もとの「ろおれんぞ」の姿を見守られた。その恭うやうやしげな容子ようすはどうぢや。その両の手のふるへざまも、尋常よのつねの事ではござるまい。おう、伴天連のからびた頬の上には、とめどなく涙が溢れ流れるぞよ。
見られい。「しめおん」。見られい。傘張の翁。御主「ぜす・きりしと」の御血潮よりも赤い、火の光を一身に浴びて、声もなく「さんた・るちや」の門に横はつた、いみじくも美しい少年の胸には、焦げ破れた衣ころものひまから、清らかな二つの乳房が、玉のやうに露あらはれて居るではないか。今は焼けただれた面輪おもわにも、自おのづからなやさしさは、隠れようすべもあるまじい。おう、「ろおれんぞ」は女ぢや。「ろおれんぞ」は女ぢや。見られい。猛火を後にして、垣のやうに佇んでゐる奉教人衆、邪淫の戒を破つたに由つて「さんた・るちや」を逐おはれた「ろおれんぞ」は、傘張の娘と同じ、眼まなざしのあでやかなこの国の女ぢや。
まことにその刹那せつなの尊い恐しさは、あたかも「でうす」の御声が、星の光も見えぬ遠い空から、伝はつて来るやうであつたと申す。されば「さんた・るちや」の前に居並んだ奉教人衆は、風に吹かれる穂麦のやうに、誰からともなく頭を垂れて、悉ことごとく「ろおれんぞ」のまはりに跪ひざまづいた。その中で聞えるものは、唯、空をどよもして燃えしきる、万丈の焔の響ばかりでござる。いや、誰やらの啜すすり泣く声も聞えたが、それは傘張の娘でござらうか。或は又自ら兄とも思うた、あの「いるまん」の「しめおん」でござらうか。やがてその寂寞じやくまくたるあたりをふるはせて、「ろおれんぞ」の上に高く手をかざしながら、伴天連の御経を誦ずせられる声が、おごそかに悲しく耳にはいつた。して御経の声がやんだ時、「ろおれんぞ」と呼ばれた、この国のうら若い女は、まだ暗い夜のあなたに、「はらいそ」の「ぐろおりや」を仰ぎ見て、安らかなほほ笑みを唇に止めたまま、静に息が絶えたのでござる。……
その女の一生は、この外に何一つ、知られなんだげに聞き及んだ。なれどそれが、何事でござらうぞ。なべて人の世の尊さは、何ものにも換へ難い、刹那の感動に極るものぢや。暗夜の海にも譬たとへようず煩悩心ぼんなうしんの空に一波をあげて、未いまだ出ぬ月の光を、水沫みなわの中に捕へてこそ、生きて甲斐ある命とも申さうず。されば「ろおれんぞ」が最期を知るものは、「ろおれんぞ」の一生を知るものではござるまいか。
二
予が所蔵に関る、長崎耶蘇会出版の一書、題して「れげんだ・おうれあ」と云ふ。蓋けだし、LEGENDA AUREA の意なり。されど内容は必しも、西欧の所謂いはゆる「黄金伝説」ならず。彼土かのどの使徒聖人が言行を録すると共に、併あはせて本邦西教徒が勇猛精進の事蹟をも採録し、以て福音伝道の一助たらしめんとせしものの如し。
体裁は上下二巻、美濃紙摺みのがみずり草体交さうたいまじり平仮名文にして、印刷甚しく鮮明を欠き、活字なりや否やを明にせず。上巻の扉には、羅甸ラテン字にて書名を横書し、その下に漢字にて「御出世以来千五百九十六年、慶長二年三月上旬鏤刻るこく也」の二行を縦書す。年代の左右には喇叭らつぱを吹ける天使の画像あり。技巧頗すこぶる幼稚なれども、亦掬きくす可き趣致なしとせず。下巻も扉に「五月中旬鏤刻也」の句あるを除いては、全く上巻と異同なし。
両巻とも紙数は約六十頁にして、載のする所の黄金伝説は、上巻八章、下巻十章を数ふ。その他各巻の巻首に著者不明の序文及羅甸ラテン字を加へたる目次あり。序文は文章雅馴がじゆんならずして、間々まま欧文を直訳せる如き語法を交へ、一見その伴天連たる西人の手になりしやを疑はしむ。
以上採録したる「奉教人の死」は、該がい「れげんだ・おうれあ」下巻第二章に依るものにして、恐らくは当時長崎の一西教寺院に起りし、事実の忠実なる記録ならんか。但、記事中の大火なるものは、「長崎港草」以下諸書に徴するも、その有無をすら明にせざるを以て、事実の正確なる年代に至つては、全くこれを決定するを得ず。
予は「奉教人の死」に於て、発表の必要上、多少の文飾を敢あへてしたり。もし原文の平易雅馴なる筆致にして、甚しく毀損きそんせらるる事なからんか、予の幸甚とする所なりと云爾しかいふ。
(大正七年八月)
神神の微笑
芥川龍之介
ある春の夕ゆうべ、Padre Organtino はたった一人、長いアビト(法衣ほうえ)の裾すそを引きながら、南蛮寺なんばんじの庭を歩いていた。
庭には松や檜ひのきの間あいだに、薔薇ばらだの、橄欖かんらんだの、月桂げっけいだの、西洋の植物が植えてあった。殊に咲き始めた薔薇の花は、木々を幽かすかにする夕明ゆうあかりの中に、薄甘い匂においを漂わせていた。それはこの庭の静寂に、何か日本にほんとは思われない、不可思議な魅力みりょくを添えるようだった。
オルガンティノは寂しそうに、砂の赤い小径こみちを歩きながら、ぼんやり追憶に耽っていた。羅馬ロオマの大本山だいほんざん、リスポアの港、羅面琴ラベイカの音ね、巴旦杏はたんきょうの味、「御主おんあるじ、わがアニマ(霊魂)の鏡」の歌――そう云う思い出はいつのまにか、この紅毛こうもうの沙門しゃもんの心へ、懐郷かいきょうの悲しみを運んで来た。彼はその悲しみを払うために、そっと泥烏須デウス(神)の御名みなを唱えた。が、悲しみは消えないばかりか、前よりは一層彼の胸へ、重苦しい空気を拡げ出した。
「この国の風景は美しい――。」
オルガンティノは反省した。
「この国の風景は美しい。気候もまず温和である。土人は、――あの黄面こうめんの小人こびとよりも、まだしも黒ん坊がましかも知れない。しかしこれも大体の気質は、親しみ易いところがある。のみならず信徒も近頃では、何万かを数えるほどになった。現にこの首府のまん中にも、こう云う寺院が聳そびえている。して見ればここに住んでいるのは、たとい愉快ではないにしても、不快にはならない筈ではないか? が、自分はどうかすると、憂鬱の底に沈む事がある。リスポアの市まちへ帰りたい、この国を去りたいと思う事がある。これは懐郷の悲しみだけであろうか? いや、自分はリスポアでなくとも、この国を去る事が出来さえすれば、どんな土地へでも行きたいと思う。支那しなでも、沙室シャムでも、印度インドでも、――つまり懐郷の悲しみは、自分の憂鬱の全部ではない。自分はただこの国から、一日も早く逃れたい気がする。しかし――しかしこの国の風景は美しい。気候もまず温和である。……」
オルガンティノは吐息といきをした。この時偶然彼の眼は、点々と木かげの苔こけに落ちた、仄白ほのじろい桜の花を捉とらえた。桜! オルガンティノは驚いたように、薄暗い木立こだちの間あいだを見つめた。そこには四五本の棕櫚しゅろの中に、枝を垂らした糸桜いとざくらが一本、夢のように花を煙らせていた。
「御主おんあるじ守らせ給え!」
オルガンティノは一瞬間、降魔ごうまの十字を切ろうとした。実際その瞬間彼の眼には、この夕闇に咲いた枝垂桜しだれざくらが、それほど無気味ぶきみに見えたのだった。無気味に、――と云うよりもむしろこの桜が、何故なぜか彼を不安にする、日本そのもののように見えたのだった。が、彼は刹那せつなの後のち、それが不思議でも何でもない、ただの桜だった事を発見すると、恥しそうに苦笑しながら、静かにまたもと来た小径へ、力のない歩みを返して行った。
× × ×
三十分の後のち、彼は南蛮寺なんばんじの内陣ないじんに、泥烏須デウスへ祈祷を捧げていた。そこにはただ円天井まるてんじょうから吊るされたランプがあるだけだった。そのランプの光の中に、内陣を囲んだフレスコの壁には、サン・ミグエルが地獄の悪魔と、モオゼの屍骸しがいを争っていた。が、勇ましい大天使は勿論、吼たけり立った悪魔さえも、今夜は朧おぼろげな光の加減か、妙にふだんよりは優美に見えた。それはまた事によると、祭壇の前に捧げられた、水々みずみずしい薔薇ばらや金雀花えにしだが、匂っているせいかも知れなかった。彼はその祭壇の後うしろに、じっと頭を垂れたまま、熱心にこう云う祈祷を凝らした。
「南無なむ大慈大悲の泥烏須如来デウスにょらい! 私わたくしはリスポアを船出した時から、一命はあなたに奉って居ります。ですから、どんな難儀に遇あっても、十字架の御威光を輝かせるためには、一歩も怯ひるまずに進んで参りました。これは勿論私一人の、能よくする所ではございません。皆天地の御主おんあるじ、あなたの御恵おんめぐみでございます。が、この日本に住んでいる内に、私はおいおい私の使命が、どのくらい難かたいかを知り始めました。この国には山にも森にも、あるいは家々の並んだ町にも、何か不思議な力が潜ひそんで居ります。そうしてそれが冥々めいめいの中うちに、私の使命を妨さまたげて居ります。さもなければ私はこの頃のように、何の理由もない憂鬱の底へ、沈んでしまう筈はございますまい。ではその力とは何であるか、それは私にはわかりません。が、とにかくその力は、ちょうど地下の泉のように、この国全体へ行き渡って居ります。まずこの力を破らなければ、おお、南無大慈大悲の泥烏須如来デウスにょらい! 邪宗じゃしゅうに惑溺わくできした日本人は波羅葦増はらいそ(天界てんがい)の荘厳しょうごんを拝する事も、永久にないかも存じません。私はそのためにこの何日か、煩悶はんもんに煩悶を重ねて参りました。どうかあなたの下部しもべ、オルガンティノに、勇気と忍耐とを御授け下さい。――」
その時ふとオルガンティノは、鶏の鳴き声を聞いたように思った。が、それには注意もせず、さらにこう祈祷の言葉を続けた。
「私わたくしは使命を果すためには、この国の山川やまかわに潜んでいる力と、――多分は人間に見えない霊と、戦わなければなりません。あなたは昔紅海こうかいの底に、埃及エジプトの軍勢ぐんぜいを御沈めになりました。この国の霊の力強い事は、埃及エジプトの軍勢に劣りますまい。どうか古いにしえの予言者のように、私もこの霊との戦に、………」
祈祷の言葉はいつのまにか、彼の唇くちびるから消えてしまった。今度は突然祭壇のあたりに、けたたましい鶏鳴けいめいが聞えたのだった。オルガンティノは不審そうに、彼の周囲を眺めまわした。すると彼の真後まうしろには、白々しろじろと尾を垂れた鶏が一羽、祭壇の上に胸を張ったまま、もう一度、夜でも明けたように鬨ときをつくっているではないか?
オルガンティノは飛び上るが早いか、アビトの両腕を拡げながら、倉皇そうこうとこの鳥を逐い出そうとした。が、二足三足ふたあしみあし踏み出したと思うと、「御主おんあるじ」と、切れ切れに叫んだなり、茫然とそこへ立ちすくんでしまった。この薄暗い内陣ないじんの中には、いつどこからはいって来たか、無数の鶏が充満している、――それがあるいは空を飛んだり、あるいはそこここを駈けまわったり、ほとんど彼の眼に見える限りは、鶏冠とさかの海にしているのだった。
「御主、守らせ給え!」
彼はまた十字を切ろうとした。が、彼の手は不思議にも、万力まんりきか何かに挟はさまれたように、一寸いっすんとは自由に動かなかった。その内にだんだん内陣ないじんの中には、榾火ほたびの明あかりに似た赤光しゃっこうが、どこからとも知れず流れ出した。オルガンティノは喘あえぎ喘ぎ、この光がさし始めると同時に、朦朧もうろうとあたりへ浮んで来た、人影があるのを発見した。
人影は見る間まに鮮あざやかになった。それはいずれも見慣れない、素朴そぼくな男女の一群ひとむれだった。彼等は皆頸くびのまわりに、緒おにぬいた玉を飾りながら、愉快そうに笑い興じていた。内陣に群がった無数の鶏は、彼等の姿がはっきりすると、今までよりは一層高らかに、何羽も鬨ときをつくり合った。同時に内陣の壁は、――サン・ミグエルの画えを描かいた壁は、霧のように夜へ呑まれてしまった。その跡には、――
日本の Bacchanalia は、呆気あっけにとられたオルガンティノの前へ、蜃気楼しんきろうのように漂って来た。彼は赤い篝かがりの火影ほかげに、古代の服装をした日本人たちが、互いに酒を酌み交かわしながら、車座くるまざをつくっているのを見た。そのまん中には女が一人、――日本ではまだ見た事のない、堂々とした体格の女が一人、大きな桶おけを伏せた上に、踊り狂っているのを見た。桶の後ろには小山のように、これもまた逞たくましい男が一人、根こぎにしたらしい榊さかきの枝に、玉だの鏡だのが下さがったのを、悠然と押し立てているのを見た。彼等のまわりには数百の鶏が、尾羽根おばねや鶏冠とさかをすり合せながら、絶えず嬉しそうに鳴いているのを見た。そのまた向うには、――オルガンティノは、今更のように、彼の眼を疑わずにはいられなかった。――そのまた向うには夜霧の中に、岩屋いわやの戸らしい一枚岩が、どっしりと聳えているのだった。
桶の上にのった女は、いつまでも踊をやめなかった。彼女の髪を巻いた蔓つるは、ひらひらと空に翻ひるがえった。彼女の頸に垂れた玉は、何度も霰あられのように響き合った。彼女の手にとった小笹の枝は、縦横に風を打ちまわった。しかもその露あらわにした胸! 赤い篝火かがりびの光の中に、艶々つやつやと浮うかび出た二つの乳房ちぶさは、ほとんどオルガンティノの眼には、情欲そのものとしか思われなかった。彼は泥烏須デウスを念じながら、一心に顔をそむけようとした。が、やはり彼の体は、どう云う神秘な呪のろいの力か、身動きさえ楽には出来なかった。
その内に突然沈黙が、幻の男女たちの上へ降った。桶の上に乗った女も、もう一度正気しょうきに返ったように、やっと狂わしい踊をやめた。いや、鳴き競っていた鶏さえ、この瞬間は頸を伸ばしたまま、一度にひっそりとなってしまった。するとその沈黙の中に、永久に美しい女の声が、どこからか厳かに伝わって来た。
「私わたしがここに隠こもっていれば、世界は暗闇になった筈ではないか? それを神々は楽しそうに、笑い興じていると見える。」
その声が夜空に消えた時、桶の上にのった女は、ちらりと一同を見渡しながら、意外なほどしとやかに返事をした。
「それはあなたにも立ち勝まさった、新しい神がおられますから、喜び合っておるのでございます。」
その新しい神と云うのは、泥烏須デウスを指しているのかも知れない。――オルガンティノはちょいとの間あいだ、そう云う気もちに励まされながら、この怪しい幻の変化に、やや興味のある目を注いだ。
沈黙はしばらく破れなかった。が、たちまち鶏の群むれが、一斉いっせいに鬨ときをつくったと思うと、向うに夜霧を堰せき止めていた、岩屋の戸らしい一枚岩が、徐おもむろに左右へ開ひらき出した。そうしてその裂さけ目からは、言句ごんくに絶した万道ばんどうの霞光かこうが、洪水のように漲みなぎり出した。
オルガンティノは叫ぼうとした。が、舌は動かなかった。オルガンティノは逃げようとした。が、足も動かなかった。彼はただ大光明のために、烈しく眩暈めまいが起るのを感じた。そうしてその光の中に、大勢おおぜいの男女の歓喜する声が、澎湃ほうはいと天に昇のぼるのを聞いた。
「大日※(「靈」の「巫」に代えて「女」、第3水準1-47-53)貴おおひるめむち! 大日※(「靈」の「巫」に代えて「女」、第3水準1-47-53)貴! 大日※(「靈」の「巫」に代えて「女」、第3水準1-47-53)貴!」
「新しい神なぞはおりません。新しい神なぞはおりません。」
「あなたに逆さからうものは亡びます。」
「御覧なさい。闇が消え失せるのを。」
「見渡す限り、あなたの山、あなたの森、あなたの川、あなたの町、あなたの海です。」
「新しい神なぞはおりません。誰も皆あなたの召使です。」
「大日※(「靈」の「巫」に代えて「女」、第3水準1-47-53)貴! 大日※(「靈」の「巫」に代えて「女」、第3水準1-47-53)貴! 大日※(「靈」の「巫」に代えて「女」、第3水準1-47-53)貴!」
そう云う声の湧き上る中に、冷汗になったオルガンティノは、何か苦しそうに叫んだきりとうとうそこへ倒れてしまった。………
その夜よも三更さんこうに近づいた頃、オルガンティノは失心の底から、やっと意識を恢復した。彼の耳には神々の声が、未だに鳴り響いているようだった。が、あたりを見廻すと、人音ひとおとも聞えない内陣ないじんには、円天井まるてんじょうのランプの光が、さっきの通り朦朧もうろうと壁画へきがを照らしているばかりだった。オルガンティノは呻うめき呻き、そろそろ祭壇の後うしろを離れた。あの幻にどんな意味があるか、それは彼にはのみこめなかった。しかしあの幻を見せたものが、泥烏須デウスでない事だけは確かだった。
「この国の霊と戦うのは、……」
オルガンティノは歩きながら、思わずそっと独り語ごとを洩らした。
「この国の霊と戦うのは、思ったよりもっと困難らしい。勝つか、それともまた負けるか、――」
するとその時彼の耳に、こう云う囁ささやきを送るものがあった。
「負けですよ!」
オルガンティノは気味悪そうに、声のした方を透すかして見た。が、そこには不相変あいかわらず、仄暗ほのぐらい薔薇や金雀花えにしだのほかに、人影らしいものも見えなかった。
× × ×
オルガンティノは翌日の夕ゆうべも、南蛮寺なんばんじの庭を歩いていた。しかし彼の碧眼へきがんには、どこか嬉しそうな色があった。それは今日一日いちにちの内に、日本の侍が三四人、奉教人ほうきょうにんの列にはいったからだった。
庭の橄欖かんらんや月桂げっけいは、ひっそりと夕闇に聳えていた。ただその沈黙が擾みだされるのは、寺の鳩はとが軒へ帰るらしい、中空なかぞらの羽音はおとよりほかはなかった。薔薇の匂におい、砂の湿り、――一切は翼のある天使たちが、「人の女子おみなごの美しきを見て、」妻を求めに降くだって来た、古代の日の暮のように平和だった。
「やはり十字架の御威光の前には、穢けがらわしい日本の霊の力も、勝利を占しめる事はむずかしいと見える。しかし昨夜ゆうべ見た幻は?――いや、あれは幻に過ぎない。悪魔はアントニオ上人しょうにんにも、ああ云う幻を見せたではないか? その証拠には今日になると、一度に何人かの信徒さえ出来た。やがてはこの国も至る所に、天主てんしゅの御寺みてらが建てられるであろう。」
オルガンティノはそう思いながら、砂の赤い小径こみちを歩いて行った。すると誰か後から、そっと肩を打つものがあった。彼はすぐに振り返った。しかし後には夕明りが、径みちを挟んだ篠懸すずかけの若葉に、うっすりと漂ただよっているだけだった。
「御主おんあるじ。守らせ給え!」
彼はこう呟つぶやいてから、徐おもむろに頭かしらをもとへ返した。と、彼の傍かたわらには、いつのまにそこへ忍び寄ったか、昨夜の幻に見えた通り、頸くびに玉を巻いた老人が一人、ぼんやり姿を煙らせたまま、徐おもむろに歩みを運んでいた。
「誰だ、お前は?」
不意を打たれたオルガンティノは、思わずそこへ立ち止まった。
「私わたしは、――誰でもかまいません。この国の霊の一人です。」
老人は微笑びしょうを浮べながら、親切そうに返事をした。
「まあ、御一緒に歩きましょう。私はあなたとしばらくの間あいだ、御話しするために出て来たのです。」
オルガンティノは十字を切った。が、老人はその印しるしに、少しも恐怖を示さなかった。
「私は悪魔ではないのです。御覧なさい、この玉やこの剣を。地獄じごくの炎ほのおに焼かれた物なら、こんなに清浄ではいない筈です。さあ、もう呪文じゅもんなぞを唱えるのはおやめなさい。」
オルガンティノはやむを得ず、不愉快そうに腕組をしたまま、老人と一しょに歩き出した。
「あなたは天主教てんしゅきょうを弘ひろめに来ていますね、――」
老人は静かに話し出した。
「それも悪い事ではないかも知れません。しかし泥烏須デウスもこの国へ来ては、きっと最後には負けてしまいますよ。」
「泥烏須デウスは全能の御主おんあるじだから、泥烏須に、――」
オルガンティノはこう云いかけてから、ふと思いついたように、いつもこの国の信徒に対する、叮嚀ていねいな口調を使い出した。
「泥烏須デウスに勝つものはない筈です。」
「ところが実際はあるのです。まあ、御聞きなさい。はるばるこの国へ渡って来たのは、泥烏須デウスばかりではありません。孔子こうし、孟子もうし、荘子そうし、――そのほか支那からは哲人たちが、何人もこの国へ渡って来ました。しかも当時はこの国が、まだ生まれたばかりだったのです。支那の哲人たちは道のほかにも、呉ごの国の絹だの秦しんの国の玉だの、いろいろな物を持って来ました。いや、そう云う宝よりも尊い、霊妙れいみょうな文字さえ持って来たのです。が、支那はそのために、我々を征服出来たでしょうか? たとえば文字もじを御覧なさい。文字は我々を征服する代りに、我々のために征服されました。私が昔知っていた土人に、柿かきの本もとの人麻呂ひとまろと云う詩人があります。その男の作った七夕たなばたの歌は、今でもこの国に残っていますが、あれを読んで御覧なさい。牽牛織女けんぎゅうしょくじょはあの中に見出す事は出来ません。あそこに歌われた恋人同士は飽あくまでも彦星ひこぼしと棚機津女たなばたつめとです。彼等の枕に響いたのは、ちょうどこの国の川のように、清い天あまの川がわの瀬音せおとでした。支那の黄河こうがや揚子江ようすこうに似た、銀河ぎんがの浪音ではなかったのです。しかし私は歌の事より、文字の事を話さなければなりません。人麻呂はあの歌を記すために、支那の文字を使いました。が、それは意味のためより、発音のための文字だったのです。舟しゅうと云う文字がはいった後のちも、「ふね」は常に「ふね」だったのです。さもなければ我々の言葉は、支那語になっていたかも知れません。これは勿論人麻呂よりも、人麻呂の心を守っていた、我々この国の神の力です。のみならず支那の哲人たちは、書道をもこの国に伝えました。空海くうかい、道風どうふう、佐理さり、行成こうぜい――私は彼等のいる所に、いつも人知れず行っていました。彼等が手本にしていたのは、皆支那人の墨蹟ぼくせきです。しかし彼等の筆先ふでさきからは、次第に新しい美が生れました。彼等の文字はいつのまにか、王羲之おうぎしでもなければ※(「ころもへん+楮のつくり」、第3水準1-91-82) 遂良ちょすいりょうでもない、日本人の文字になり出したのです。しかし我々が勝ったのは、文字ばかりではありません。我々の息吹いぶきは潮風しおかぜのように、老儒ろうじゅの道さえも和やわらげました。この国の土人に尋ねて御覧なさい。彼等は皆孟子もうしの著書は、我々の怒に触ふれ易いために、それを積んだ船があれば、必ず覆くつがえると信じています。科戸しなとの神はまだ一度も、そんな悪戯いたずらはしていません。が、そう云う信仰の中うちにも、この国に住んでいる我々の力は、朧おぼろげながら感じられる筈です。あなたはそう思いませんか?」
オルガンティノは茫然と、老人の顔を眺め返した。この国の歴史に疎うとい彼には、折角せっかくの相手の雄弁も、半分はわからずにしまったのだった。
「支那の哲人たちの後のちに来たのは、印度インドの王子悉達多したあるたです。――」
老人は言葉を続けながら、径みちばたの薔薇ばらの花をむしると、嬉しそうにその匂を嗅かいだ。が、薔薇はむしられた跡にも、ちゃんとその花が残っていた。ただ老人の手にある花は色や形は同じに見えても、どこか霧のように煙っていた。
「仏陀ぶっだの運命も同様です。が、こんな事を一々御話しするのは、御退屈を増すだけかも知れません。ただ気をつけて頂きたいのは、本地垂跡ほんじすいじゃくの教の事です。あの教はこの国の土人に、大日※(「靈」の「巫」に代えて「女」、第3水準1-47-53)貴おおひるめむちは大日如来だいにちにょらいと同じものだと思わせました。これは大日※(「靈」の「巫」に代えて「女」、第3水準1-47-53)貴の勝でしょうか? それとも大日如来の勝でしょうか? 仮りに現在この国の土人に、大日※(「靈」の「巫」に代えて「女」、第3水準1-47-53)貴は知らないにしても、大日如来は知っているものが、大勢あるとして御覧なさい。それでも彼等の夢に見える、大日如来の姿の中うちには、印度仏ぶつの面影おもかげよりも、大日※(「靈」の「巫」に代えて「女」、第3水準1-47-53)貴が窺うかがわれはしないでしょうか? 私わたしは親鸞しんらんや日蓮にちれんと一しょに、沙羅双樹さらそうじゅの花の陰も歩いています。彼等が随喜渇仰ずいきかつごうした仏ほとけは、円光のある黒人こくじんではありません。優しい威厳いげんに充ち満ちた上宮太子じょうぐうたいしなどの兄弟です。――が、そんな事を長々と御話しするのは、御約束の通りやめにしましょう。つまり私が申上げたいのは、泥烏須デウスのようにこの国に来ても、勝つものはないと云う事なのです。」
「まあ、御待ちなさい。御前おまえさんはそう云われるが、――」
オルガンティノは口を挟はさんだ。
「今日などは侍が二三人、一度に御教おんおしえに帰依きえしましたよ。」
「それは何人なんにんでも帰依するでしょう。ただ帰依したと云う事だけならば、この国の土人は大部分悉達多したあるたの教えに帰依しています。しかし我々の力と云うのは、破壊する力ではありません。造り変える力なのです。」
老人は薔薇の花を投げた。花は手を離れたと思うと、たちまち夕明りに消えてしまった。
「なるほど造り変える力ですか? しかしそれはお前さんたちに、限った事ではないでしょう。どこの国でも、――たとえば希臘ギリシャの神々と云われた、あの国にいる悪魔でも、――」
「大いなるパンは死にました。いや、パンもいつかはまたよみ返るかも知れません。しかし我々はこの通り、未だに生きているのです。」
オルガンティノは珍しそうに、老人の顔へ横眼を使った。
「お前さんはパンを知っているのですか?」
「何、西国さいこくの大名の子たちが、西洋から持って帰ったと云う、横文字よこもじの本にあったのです。――それも今の話ですが、たといこの造り変える力が、我々だけに限らないでも、やはり油断はなりませんよ。いや、むしろ、それだけに、御気をつけなさいと云いたいのです。我々は古い神ですからね。あの希臘ギリシャの神々のように、世界の夜明けを見た神ですからね。」
「しかし泥烏須デウスは勝つ筈です。」
オルガンティノは剛情に、もう一度同じ事を云い放った。が、老人はそれが聞えないように、こうゆっくり話し続けた。
「私わたしはつい四五日前まえ、西国さいこくの海辺うみべに上陸した、希臘ギリシャの船乗りに遇あいました。その男は神ではありません。ただの人間に過ぎないのです。私はその船乗と、月夜の岩の上に坐りながら、いろいろの話を聞いて来ました。目一つの神につかまった話だの、人を豕いのこにする女神めがみの話だの、声の美しい人魚にんぎょの話だの、――あなたはその男の名を知っていますか? その男は私に遇あった時から、この国の土人に変りました。今では百合若ゆりわかと名乗っているそうです。ですからあなたも御気をつけなさい。泥烏須デウスも必ず勝つとは云われません。天主教てんしゅきょうはいくら弘ひろまっても、必ず勝つとは云われません。」
老人はだんだん小声になった。
「事によると泥烏須デウス自身も、この国の土人に変るでしょう。支那や印度も変ったのです。西洋も変らなければなりません。我々は木々の中にもいます。浅い水の流れにもいます。薔薇ばらの花を渡る風にもいます。寺の壁に残る夕明ゆうあかりにもいます。どこにでも、またいつでもいます。御気をつけなさい。御気をつけなさい。………」
その声がとうとう絶えたと思うと、老人の姿も夕闇の中へ、影が消えるように消えてしまった。と同時に寺の塔からは、眉をひそめたオルガンティノの上へ、アヴェ・マリアの鐘が響き始めた。
× × ×
南蛮寺なんばんじのパアドレ・オルガンティノは、――いや、オルガンティノに限った事ではない。悠々とアビトの裾すそを引いた、鼻の高い紅毛人こうもうじんは、黄昏たそがれの光の漂ただよった、架空かくうの月桂げっけいや薔薇の中から、一双の屏風びょうぶへ帰って行った。南蛮船なんばんせん入津にゅうしんの図を描かいた、三世紀以前の古屏風へ。
さようなら。パアドレ・オルガンティノ! 君は今君の仲間と、日本の海辺うみべを歩きながら、金泥きんでいの霞に旗を挙げた、大きい南蛮船を眺めている。泥烏須デウスが勝つか、大日※(「靈」の「巫」に代えて「女」、第3水準1-47-53)貴おおひるめむちが勝つか――それはまだ現在でも、容易よういに断定だんていは出来ないかも知れない。が、やがては我々の事業が、断定を与うべき問題である。君はその過去の海辺から、静かに我々を見てい給え。たとい君は同じ屏風の、犬を曳ひいた甲比丹カピタンや、日傘をさしかけた黒ん坊の子供と、忘却の眠に沈んでいても、新たに水平へ現れた、我々の黒船くろふねの石火矢いしびやの音は、必ず古めかしい君等の夢を破る時があるに違いない。それまでは、――さようなら。パアドレ・オルガンティノ! さようなら。南蛮寺のウルガン伴天連バテレン!
(大正十年十二月)
底本:「芥川龍之介全集4」ちくま文庫、筑摩書房
1987(昭和62)年1月27日第1刷発行
1993(平成5)年12月25日第6刷発行
底本の親本:「筑摩全集類聚版芥川龍之介全集」筑摩書房
1971(昭和46)年3月~1971(昭和46)年11月
入力:j.utiyama
校正:かとうかおり
1998年12月19日公開
2004年3月10日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
底本:「現代日本文学大系 43 芥川龍之介集」筑摩書房
1968(昭和43)年8月25日初版第1刷発行
入力:j.utiyama
校正:八木正三
1998年6月14日公開
2010年11月4日修正
青空文庫作成ファイル:
このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫(http://www.aozora.gr.jp/)で作られました。入力、校正、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。
●表記について
このファイルは W3C 勧告 XHTML1.1 にそった形式で作成されています。
[#…]は、入力者による注を表す記号です。
●図書カード