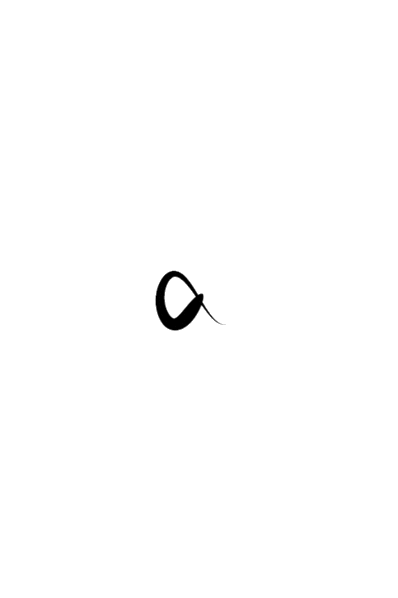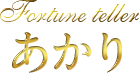安心・平穏・喜び・夢・希望・幸せ 占あかり いつもあなたの全てが 人生の 価値ある ひと時に、、、 | ★★ 占い鑑定 相談料金 ★★ 一般 1500円 30分 (30分から10分ごと500円追加) ご予約・お問合せ (10~22時受付) ✉ メール (24時間受付) |
お知らせ
占い師たかしのメルマガ配信中!
ココでしか聞けない裏話、日常に役立つあれこれ、メルマガを通じ無料で配信しています。占いの知識、時事、仕事、金運アップ術、男と女、家族、自信と誇りの回復、人生の幸せあれこれ、楽しく、また様々な情報盛りだくさん配信中です。
▼ ご登録はこちら ▼
藤原山蔭(表氏)80世(八咫烏)による史実を考察
明智光秀と細川ガーシャ、織田信長(ジョルダーノ・ブルーノ)コジモ1世と斎藤道三について
参考資料
上様団子 trivia and pursuits about Oda Nobunagaの記事より
織田信長

この記事のヒントはいつものOtsukeさんから得たものです。彼はある投稿で、ジョヴァンニ・ニッコロが描いた有名な信長の肖像画は信長の肖像画ではなく、明治時代に撮られた親族の写真ではないかと何気なく言っていました。
衝撃が走りました。
私たちファンガールを歴史的な満足感でうならせた肖像画が、本当の信長ではなかった可能性です。
そこで今日はインターネットを開いて、この問題を詳しく調べることにしました。
まず第一に、この肖像画が本物の信長の実際の肖像画ではないという事実は事実です。
この作品は信長が亡くなってからずっと後の1583年以降のもので、私たちのイエズス会の画家がマカオに到着したのは1582年になってからでした。
元の話によると、この肖像画は信長の親族で、息子の信雄が経営していた織田家の人物の説明に従って描かれたとのことです。
物語はこうです。このイエズス会のイタリア人画家の技術と、彼が代表する新しさを知った信雄は、彼の死後、高名な前任者の肖像画を彼に依頼し、ニッコロ(ポルトガル語なので「ニコラオ」とも表記される)は木炭で我らが上様のこの生き生きとした描写を描きました。
数世紀後、織田家は天童藩への移住を余儀なくされ、その時になって初めてこの肖像画が一族の遺産から現れました。
それは家宝と宣言され、菩提寺に納められ、さらに明治時代には都合よく写真が撮られ、保存されていました。
明らかに元の肖像画は火事で焼失し、写真だけが救われ、その写真は現在、山形県にある天童織田家の菩提寺である三宝寺に納められています。怪しいと思いませんか?
ジョヴァンニ・ニッコロについて調べてみましたが、ウィキペディアの小さな伝記以外にはあまり見つけられませんでした。ジョヴァンニは、長崎の最初の美術学校の巨匠であり、西洋美術への情熱をアジアにもたらした人物であるにもかかわらず、彼の作品とされる絵画はほとんど存在しないことに私はすぐに気付きました。このことを真剣に受け止めた
日本語版ウィキペディアは、有名な「西洋の王の騎馬像」(日本では非常に人気のあるテーマ)を描いた屛風が彼の作品であると認めることができるとしていますが、もしそれが本当なら、私たちの肖像画の写実的なスタイルとの類似性はほとんど見当たりません。 しかし、ジョヴァンニがポルトガル起源の芸術言語と結びついたその古風な絵画スタイルに従ったことは事実です。彼の中国と日本の弟子たち が作った作品に倣うと、
イエズス会の宣教活動の足跡として残された、類似したマニエラと言語が確かに見られます。そこから、ジョヴァンニの弟子たちが師のスタイルを完全に模倣するようになったと信じることができます。
スタイルに従うことは「自然を模倣」できないことを意味しないのは事実ですが、ジョヴァンニが信雄と対面したとしても、彼がイエズス会の芸術スタイルで有名であり、それが信雄の期待通りだったと仮定すると、ジョヴァンニがあえてそのような写実的な肖像画を制作した可能性はほとんどありません。
以下は、信長の肖像画、ジョヴァンニ・ニッコロの作とされる王の一人の肖像画、そして当時日本で非常に人気があり、アイコンとして広く普及していたイエスの「世界の救世主」の絵画(1597年)の比較です。



ジョルダーノ ブルーノ(Giordano-Bruno)と織田信長似てませんか?ほぼ同時代です。

織田信長

ジョルダーノ ブルーノ
(Giordano-Bruno)
生誕 1548年
ナポリ王国 ノーラ
死没 1600年2月17日
教皇領 ローマ
時代 ルネサンス哲学
地域 ヨーロッパ
研究分野 哲学
自然哲学
天文学
記憶術
本能寺の変によって自害したとされている織田信長ですが、その後遺体が発見されなかったため、噂となったのが「織田信長の生存説」です。
当時の本能寺は、大伽藍をもつ大きな寺院で周囲には高い塀があり、堀も巡らせてありました。
安全面だけではなく種子島にも多くの信者がいたため、鉄砲や火薬などを手に入れるために大変有利だったようです。
そのため、信長は寺領を安堵し、京都での滞在場所として本能寺を利用していました。
そんな寺院であれば抜け道や隠し通路の一つや二つあっても不思議ではなく、信長は隠し通路を使って本能寺を脱出し、生き延びていたというのです。
信長の生存説には他にも色々あるのですが、その中の一つで海外へと渡り「ジョルダーノ・ブルーノ」になったのではという噂があります。
但し、二人についての情報を知る限りでは完全に別人です。何故、そんな二人にこのような都市伝説が浮上したのかというと「顔が似ている」という部分です。
日本には源義経が海を渡りチンギス・ハンとなったという伝説もありますから、信長にそんな噂が流れたとしても不思議ではありません。夢がありますよね。
1548年~1600年2月17日
ナポリ王国のノーラで生まれ、14歳の時にナポリに引っ越しナポリ大学で学びました。17歳の時にドミニコ会に入会し、フィリッポ・ブルーノからジョルダーノ・ブルーノと名を改めました。
ジョルダーノ・ブルーノ1572年には司祭となり、1575年には神学博士となりました。
ジョルダーノ・ブルーノは様々な思想・哲学から独自の哲学を生み出しましたが、1576年「異端の嫌疑」をかけられて逃走、しばらく放浪生活を送りました。
その後、1585年にパリへと戻りましたが、アリストテレスの自然哲学を批判した「120のテーゼ」が問題視され、1592年に異端審問所に連行されました。
そのまま7年の歳月を牢獄で過ごし、異端審問が行われましたが自説の完全な撤回を求められましたがジョルダーノはそれを拒否。
さらに魔術・占星術の信奉やマリアの処女性の否定などを含めて24もの罪に問われ、1600年1月8日に死刑が確定し、同年2月17日に火刑に処されました。
しかし、ジョルダーノの処刑については20世紀になってから再検証がなされ、1979年にカトリック教会が公式に異端判決を取り消しています。
—————————————————————————
コジモ1世

在位 1569年 – 1574年
出生 1519年6月11日
死去 1574年4月21日(54歳没)
配偶者 エレオノーラ・ディ・トレド
カミッラ・マルテッリ
子女 一覧参照
家名 メディチ家
父親 ジョヴァンニ・デッレ・バンデ・ネーレ
母親 マリア・サルヴィアティ
コジモ1世(イタリア語: Cosimo I de’ Medici, 1519年6月11日 – 1574年4月21日)は、初代トスカーナ大公で、フィレンツェの名門メディチ家の1人。子はフランチェスコ1世。
沿革
メディチ傍系であり、勇敢な傭兵隊長として知られた「黒隊長」ジョヴァンニ(1498年 – 1526年)と、その妻でロレンツォ・デ・メディチの孫にあたるマリーアの間に生まれます。また、ルネサンス期の女傑として知られるカテリーナ・スフォルツァの孫に当たります。1537年、フィレンツェ公アレッサンドロ(ローマ教皇クレメンス7世の庶子)が暗殺された後、18歳のコジモがフィレンツェ公を継ぎます。こうしてコジモ率いるフィレンツェ公国は神聖ローマ帝国ハプスブルク家の支援のもと、フィレンツェの中央集権体制を確立していきます。
トスカーナ公となるとイタリア戦争に関わっていき、カール5世の神聖ローマ帝国側に組してスペイン軍と共にフランスと結んだシエーナ共和国を攻撃し1555年にシエーナを占領しました。そして、1559年のカトー・カンブレジ条約によりスペインに貸していた膨大な債権と引き換えにシエーナ共和国とシエーナ公の地位を手に入れ、併合した。さらに1569年にはローマ教皇ピウス5世により初代トスカーナ大公に任じられここにトスカーナ大公国が成立しました。
さらに海軍を創設した。この海軍は1571年のレパントの海戦にも参戦しています。しかしスペインの警戒もあり、公国は完全には自立できなかった。コジモ1世の最大の功績は、首都フィレンツェの都市改造事業であり、現在のウフィツィ美術館や、ヴァザーリの回廊(英語版)などを建設し、今日のフィレンツェの景観を作り上げています。
ジョルジョ・ヴァザーリ、アニョロ・ブロンズィーノらを宮廷画家として迎える。有名なヴァザーリの『画家・彫刻家・建築家列伝』はコジモに捧げられており、ブロンズィーノはコジモや妻エレオノーラなど一家の肖像を多く残した。 また、ミケランジェロの葬儀(1564年)を行った。コジモ1世の時代、再びフィレンツェでのルネサンス文化が花開いたといえます。
1562年、2人の子と妃エレオノーラ・ディ・トレドがマラリアで相次いで死去。これ以後、コジモ1世の晩年は悲劇とスキャンダルに見舞われる事となります。1569年、教皇ピウス5世により初代トスカーナ大公となりました。
晩年は半身不随となり、また再婚するが家庭的に恵まれませんでした。トスカーナ大公は子のフランチェスコが継ぎました。
子女
マリーア(1540年 – 1557年)
フランチェスコ1世(1541年 – 1587年) – トスカーナ大公
イザベッラ(1542年 – 1576年)
ジョヴァンニ(1543年 – 1562年)
ルクレツィア(1545年 – 1561年)
ピエトロ(1546年 – 1547年)
ガルツィア(1547年 – 1562年)
アントニオ(1548年、夭折)
フェルディナンド1世(1549年 – 1609年) – トスカーナ大公
アンナ(1553年、夭折)
ピエトロ(1554年 – 1604年)
関連事項
メディチ家
トスカーナ大公国
先代
アレッサンドロ
フィレンツェ公
1537年 – 1569年
次代
(トスカーナ大公国に
発展的解消)
先代
新設
トスカーナ大公
1569年 – 1574年
次代
フランチェスコ1世
典拠管理データベース
全般
FASTISNIVIAF
国立図書館
ノルウェースペインフランスBnF dataカタルーニャドイツイタリアイスラエルベルギーアメリカスウェーデン日本チェコオーストラリアギリシャクロアチアオランダポーランドバチカン
学術データベース
CiNii BooksCiNii Research
芸術家
オランダ美術史研究所データベースULAN
人物
トレッカーニ百科事典ドイッチェ・ビオグラフィーTrove(オーストラリア)
1
その他
RISMSNACIdRef
—————————————————————————————————
斎藤道三

斎藤道三像(常在寺蔵)

時代 戦国時代
生誕 明応3年(1494年)?
永正元年(1504年)?
死没 弘治2年4月20日(1556年5月28日)
改名 長井規秀、斎藤利政、道三(号)
別名 通称:新九郎
戒名 円覚院殿一翁道三日抬大居士神儀
墓所 常在寺(岐阜県岐阜市)、道三塚(岐阜県岐阜市)
官位 左近大夫、山城守
幕府 室町幕府美濃国守護代
主君 長井景弘、土岐頼芸
氏族 長井氏、斎藤氏
父母 父:長井新左衛門尉(旧来の説では松波基宗とも)
母:不明
妻 小見の方
深芳野
稲葉氏(稲葉良通の姉妹)
子 義龍、孫四郎、喜平次、利堯、利治、濃姫(織田信長正室)他
詳しくは、wikihttps://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%8E%E8%97%A4%E9%81%93%E4%B8%89