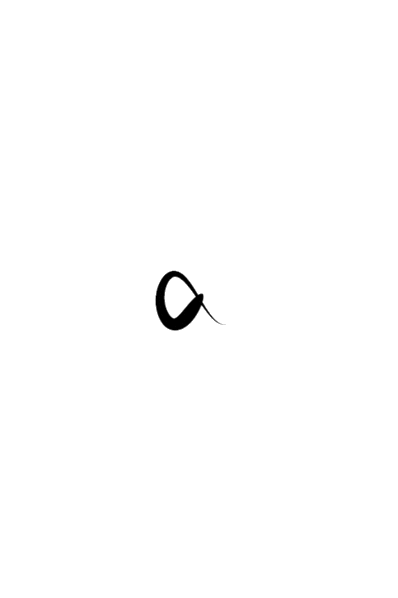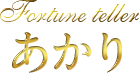安心・平穏・喜び・夢・希望・幸せ 占あかり いつもあなたの全てが 人生の 価値ある ひと時に、、、 | ★★ 占い鑑定 相談料金 ★★ 一般 1500円 30分 (30分から10分ごと500円追加) ご予約・お問合せ (10~22時受付) ✉ メール (24時間受付) |
お知らせ
占い師たかしのメルマガ配信中!
ココでしか聞けない裏話、日常に役立つあれこれ、メルマガを通じ無料で配信しています。占いの知識、時事、仕事、金運アップ術、男と女、家族、自信と誇りの回復、人生の幸せあれこれ、楽しく、また様々な情報盛りだくさん配信中です。
▼ ご登録はこちら ▼
【日本の文化、考察】2月の異名 如月 如月(にょげつ)と 衣更着(きさらぎ)は、意味と由来の決定的な違い。如月の異名は、日本の季節に合わないし、由来も日本独自のものでは全くないので、ふさわしくありません。日本の2月の情感あふれる季節感のある異名は、衣更着や梅見月など他に多数あるのですが、なぜ如月が一般的になっているのでしょう?
2月の異名といえば、「如月(きさらぎ)」が最も一般的ですが、
漢字そのものからは、どのような意味を示しているのか、分かりづらいですね。
漢字と表す意味の由来が異なるため季節感にもずれがあり暦の役目を果たしていません。
現在もなお混乱したままです。
実は、如月(きさらぎ)の由来は、まだまだ寒さが厳しい時期のために、
更に衣を重ね着するという意味から「衣更着(きさらぎ)」になった
という説が最も有力とされています。
日本の季節に合いますね。
※平安末期の歌人藤原清輔が、歌論書『奥儀抄』で「更に衣を重ね着る」という意に解いたと言われている。
チャイナから日本に入ってきた暦は、農林水産業に全く使い物にならなかったのです。
暦のこの問題に、チャレンジを挑んだ人が安倍晴明氏だったわけです。
その研究成果が完成したのが、現在は旧暦、旧などと無礼な名前で呼ばれていますが、
日本の季節や文化に合った、しっかり高度に完成した和暦日本歴の始まりだったわけです。
日本の季節にそって農林水産業は行われるために、季節の予測が正確になって来た為、より安定した生産収穫が得られるようになりました。
それで、天皇より、国民の命を支える立派な功績を認められ、
この自然研究所(陰陽道)の一階の下級階層からトップになったのでした。
神業のような魔術師かのように騒がれ始めたのは、
安倍晴明氏が、亡くなった後からだそうです。
では、なぜ「如月」の漢字が使われているかというと、
チャイナの2月の異名「如月(にょげつ)」、、から来ています。
現在、旧暦と呼ばれている和暦日本歴とは発祥地が全く関係がありません。
日本人として重要度の優先順位を考え、明確な基準を定め、けじめをつけておきましょう。
そもそも、暦は、国民の農産物の生産に関わる国民にとって命を守る重要な存在です。
ですので、チャイナの暦を日本へ利用してみたのですが、これが、先ほどお話ししたように、全く役に立たず困っていたところに、日本の季節に合った、日本独自の暦づくりに安倍晴明が着手研究し高度に季節に合った暦が完成しました和暦、日本歴です。
ですので、まず、チャイナの季節に合わせて作られた暦につけられた名前を残してた。と考えられますので、日本の季節の異名ではありません。
その後、日本独自のものとなった季節の味わい豊かに表現された和暦の言葉とは、
全く別のものである為、如月を他の異名の位置にし、日本の季節に情感あふれる異名があるのですから、一般に使う2月の異名を考え直す必要があると考えます。
先程申しましたように、
如月(きさらぎ)の由来は、まだまだ寒さが厳しい時期のために、
更に衣を重ね着するという意味から「衣更着(きさらぎ)」になった
という説が最も有力とされています。実際の日本の季節にぴったり来ます。
如月(にょげつ)には、寒い冬が終わり、
春に向かって万物が動き始める時期という意味があります。
こちらは、全く季節がずれています。日本の2月の季節に合いません。
ですので、日本の2月の異名は「衣更着(きさらぎ)」か梅見月など他の異名に定義し直すべきと考えています。
同じ漢字を使っているのですが、
「きさらぎ」と「にょげつ」で表している意味は、
もともと、このように全く由来も意味も違うわけです。

2月には、如月の他にも様々な異名があるので、季節に合わない異名を使う必要はありません。梅見月など季節感じますね。ご紹介していきます。
「令月(れいげつ)」は何をするにもいい月、素晴らしい月という意味があり、新元号「令和」の由来ともなりました。
旧暦で1月から3月が春とされ、2月はその真中の月ということから、「仲春(ちゅうしゅん)」という呼び名もあります。
「梅見月(うめみづき)」、「雪消月(ゆききえつき)」、「木芽月(このめつき)」など、
厳しい寒さの中にある小さな春を思い起こさせる言葉も多くあります。
秋にやってきた渡り鳥の雁(がん)が春が近づきシベリアへ帰っていく頃ということから、
「雁帰月(かりかえりづき)」という呼び方もあるようです。
「恵風(けいふう)」は、漢字の通り恵みの風、春風という意味があります。
厳しい寒さの時期を表す言葉、少しずつ春へと向かう様子を表す言葉が共存しており、
季節が移ろい始める時期であることが感じ取れるのではないでしょうか。
あなたならどれを選びますか?